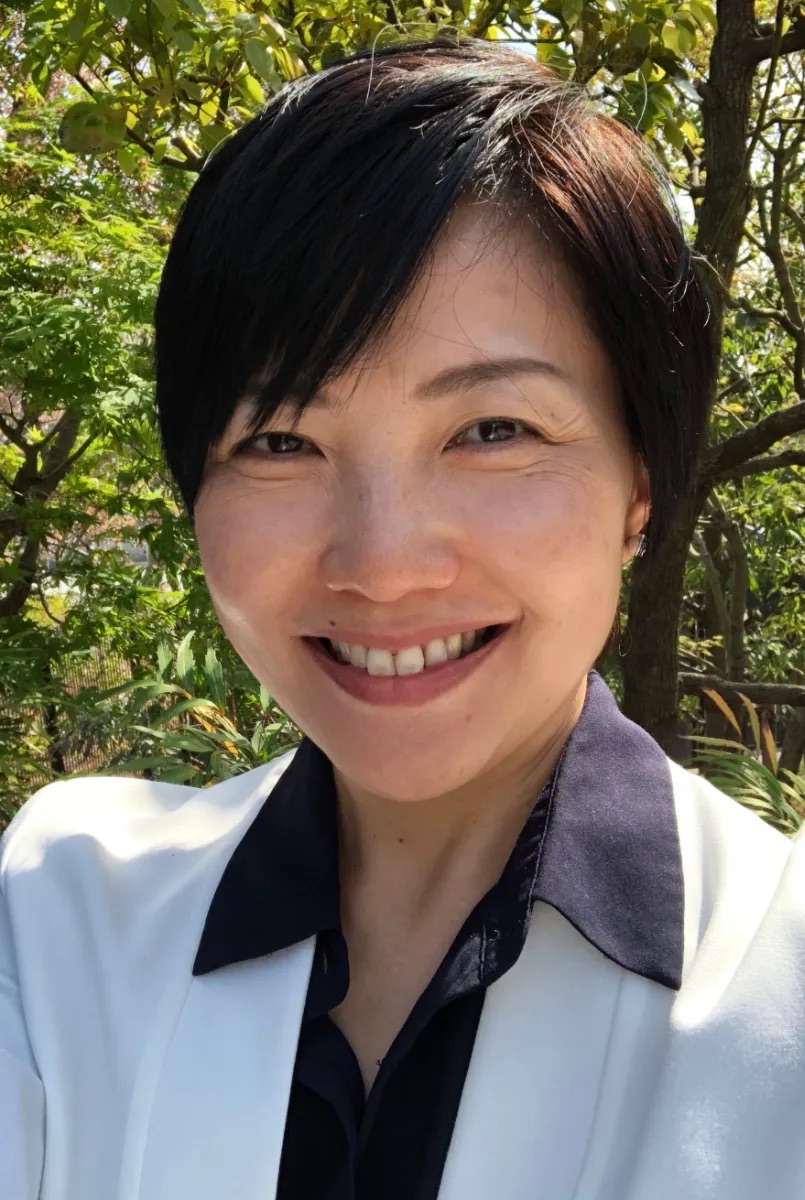ミミズコンポストは難しい?メリット・デメリットを解説

たいら 由以子
・ 10分で読める
Index

ミミズコンポストをご存じですか?生ごみをミミズに食べてもらい、栄養たっぷりの堆肥を作る方法です。エコで自然にもやさしい方法として注目されていますが、「手間がかかりそう」「ミミズってちょっと苦手」と感じる方もいるかもしれません。
そこで本記事では、ミミズコンポストのしくみやメリット・デメリットをやさしく解説し、初心者でも取り入れやすい方法をご紹介します。ミミズコンポストの特徴を理解したうえで、気軽に始められるおすすめの方法もあわせて紹介します。ぜひ参考にしてみてくださいね。
この記事は以下の方におすすめです▼
- ごみの削減やエコな暮らしに興味がある方
- コンポストに挑戦してみたいけれど不安がある方
- ミミズコンポストに関心がある初心者の方
この記事は以下の情報が得られます▼
- ミミズコンポストの仕組みや基本知識
- ミミズコンポストのメリット・デメリット
- 初心者でも取り入れやすいLFCコンポストの特徴
ミミズコンポストとは

最近、ごみの削減やフードロスへの関心が高まり、家庭でコンポストを始める人が増えています。コンポストとは、生ごみなどの有機物を微生物の力で分解し、栄養豊かな堆肥をつくる方法です。
その中でも注目されているのが「ミミズコンポスト」。微生物だけでなくミミズの力も借りることで、分解がよりスムーズに進むのが特長です。ミミズが生ごみを食べ、排せつすることで土壌の改良にもつながるとされています。
海外ではヨーロッパやオーストラリアなどを中心に家庭での導入が進んでおり、都市部でもできるサステナブルな選択肢として注目が集まっています。
ミミズの種類と生態
ミミズコンポストに使われるミミズには、実は種類ごとに向き・不向きがあります。なかには堆肥づくりにとても適した種類もいて、よりスムーズに生ごみを分解してくれる頼もしい存在となっています。
ここでは、コンポストにぴったりなミミズの種類や、ミミズがどのように生活し分解を助けてくれているのか、その生態について紹介していきます。
ミミズの種類
ミミズは、世界中に何千種類も存在するといわれています。生息する場所によって「表層性種」「表層採食地中性種」「地中性種」の3つに分類され、それぞれ特徴が異なります。日本の公園や山などでよく見かけるのは大きくて太めの「フトミミズ」という種類ですが、これはコンポストにはあまり向いていません。
コンポストに適しているのは、表層に生息し、生ごみなどをよく食べる「シマミミズ」という種類。フトミミズに比べて細く小さく、釣りのエサとしてもおなじみのミミズです。釣具店やネット販売で生きたまま購入することもできます。
ミミズの生態
ミミズは地中に生息する生きものですが、コンポストの中でもとても活発に活動しています。シマミミズの体長は5〜10cmほどで、重さは1g前後と小柄ですが、食べる力や繁殖力は驚くほど高いのが特徴です。
彼らの1日は「動く→食べる→出す」の繰り返し。移動することで土を耕し、生ごみを食べて分解し、排せつ物はそのまま栄養たっぷりの堆肥になります。さらにミミズ自身が寿命を迎えた後も、その死骸が土の栄養となり無駄のない循環が生まれます。
繁殖力の高いシマミミズは、環境が整えば自然に数が増えます。目安として、最初は500匹ほどからスタートするのが一般的ですが、たとえば毎日500g程度の生ごみを処理する場合には、約2,500匹のミミズが必要になる場合もあるようです。
そのため、まずは少量から始めて、ミミズが増えていく様子を見ながら調整していくのがおすすめです。
ミミズコンポストに入れられるもの・入れてはいけないもの
ミミズコンポストでは、家庭から出るさまざまな生ごみをエサとして活用できます。ただし、ミミズにも好き嫌いがあるためすべての食品や素材が向いているわけではなく、入れるものを選ぶことが大切です。以下に、代表的な例をまとめました。
| 入れてよいもの | あまり入れないほうがよいもの | 入れてはいけないもの |
|
|
|
大量の肉は虫が湧きやすく、匂いの原因になることも。また薬を飲んでいる犬、牛のふんを与えるとミミズが死んでしまうため注意が必要です。
バランスよく多様な素材を与えることで、栄養豊富な堆肥に仕上がります。心配な場合は、まず少量から試して様子を見るのがおすすめです。
ミミズコンポストのメリット

ミミズコンポストには、自然にやさしいだけでなく、日々の暮らしにうれしいメリットがたくさんあります。ここでは、代表的な5つの魅力をご紹介します。
悪臭が出にくい
ミミズコンポストは、適量の生ごみを入れていれば、いやな臭いがほとんど発生しません。ミミズがすぐに食べて分解を始めるため、生ごみが腐る前に処理され悪臭の原因が抑えられます。
実際に、キッチンの近くやベランダだけでなく、仕事部屋などの室内に設置している人もいるほどです。虫やにおいが心配でコンポストをためらっていた方にも、安心して取り入れやすい方法です。
良質な堆肥ができる
ミミズコンポストでできる堆肥は、微生物だけで分解したものと比べて、ふかふかで通気性のよい土に仕上がります。ミミズの排せつ物によって「団粒構造」と呼ばれる粒のかたまりが生まれ、植物の根が張りやすくなるのです。
また、コンポスト容器の底にたまる液体には栄養が豊富に含まれており、「ミミズ液肥」として活用できます。水で10倍程度に薄めて、野菜や観葉植物の液体肥料として使うのがおすすめです。
毎日かき混ぜなくて良い
一般的なコンポストでは、微生物が活動しやすいように毎日かき混ぜて酸素を供給する必要があります。特に密閉容器では、酸素不足になると悪臭や分解の遅れにつながることもあるでしょう。
一方で、ミミズコンポストならミミズが日々動き回ることで、自然と中のごみがかき混ぜられます。ミミズが通ったあとは酸素が入り込みやすいため、堆肥化もスムーズに進みやすくなります。
毎日のお世話が少なくて済むので、忙しい方やコンポスト初心者にもぴったり。負担を感じずに、無理なく続けやすいのが魅力です。
省スペースでできる
ミミズコンポストは、広い庭や畑がなくても始められるのが魅力です。たとえば、1日あたり500gほどの生ごみを出す3~4人家族でも、一辺が約40cm四方のコンテナひとつで運用できるとされています。
大がかりな設備は不要でベランダや玄関横、室内の隅など、省スペースでの設置が可能です。場所をとらないため、マンション暮らしの方や家庭菜園の延長で始めたい方にもぴったりです。
観察するのが面白い
ミミズコンポストは、ただごみを減らすだけでなく、その過程を「見て楽しむ」こともできます。生ごみが少しずつ分解されていく様子は、想像以上に興味深く、続けるうちにミミズに愛着がわいてくるのも特徴の一つです。なかにはペットのように名前をつけて育てている方もいます。
子どもの自由研究や食育のきっかけとして始める家庭も多く、楽しさを感じながらごみ処理や食べ残しへの意識を自然と変えられる点も、ミミズコンポストならではの魅力です。
ミミズコンポストのデメリット
ミミズコンポストには多くのメリットがありますが、始める前に知っておきたい注意点もいくつかあります。あらかじめ理解しておくことで、トラブルを防ぎながら、より安心して続けることができます。
処理できないものがある
ミミズコンポストでは多くの生ごみを処理できますが、すべてを入れてよいわけではありません。油を多く含むものや香辛料などの刺激物、汁気の多いものはミミズに負担がかかり分解がうまく進まないことがあります。
また、1日に処理できるごみの量にも限度があります。入れる量は様子を見ながら調整することが大切です。そのため、「ごみをすべてゼロにする」というよりは「無理のない範囲でエコな暮らしを続けていく方法」として取り入れるといいでしょう。
病原菌や害虫、雑草が残ることもある
一般的なコンポストでは、微生物の働きによって内部が20~60度ほどに温まり、ときには湯気が出るほど高温になります。この熱によって病原菌や害虫の卵、雑草の種などが死滅しやすく、安心して堆肥として使えるのが特長です。
一方、ミミズが快適に活動できる温度は10~28度と比較的低め。温度が上がりすぎるとミミズが弱ってしまうため、高温にはできません。そのため、ミミズコンポストでは一部の病原菌や雑草の種が残ることがありますが、これは仕組み上、避けられないこととして理解しておきましょう。
暑さに弱い
先ほどお伝えしたようにミミズは高温に弱いため、夏場の管理には少し注意が必要です。活動に適した温度の10~28度以上を超えるとミミズの動きが鈍くなったり、弱ってしまったりすることもあります。
近年は気温が30度を超える日も多いため、屋外に設置している場合は、直射日光を避けたり風通しの良い場所に移したりする工夫が必要です。ベランダや玄関先での運用が難しい場合は、夏の間だけ室内に置くのも一つの方法です。無理のない範囲で調整しながら、ミミズが過ごしやすい環境を整えてあげましょう。
まずはLFCのコンポストから始めてみませんか
ミミズコンポストは、ごみを減らしながら栄養たっぷりの堆肥がつくれる魅力的な方法ですが、実際にはミミズの健康管理や環境づくりなど、少し手間のかかる一面もあります。微生物の働きだけでなく、ミミズの性質も理解しながら続けていく必要があるため、メリットは多いですが初心者にとってハードルが高く感じられるかもしれません。
そんな方におすすめなのが、LFCコンポストです。ファスナー付きのバッグ型容器で、虫が入りにくく、臭いも気になりにくい構造になっています。ベランダなど限られたスペースにも設置できるため、都心部の家庭菜園にもぴったりです。
さらに、LINEで気軽に相談できるサポート体制も整っており「初めてでどうしてよいのかわからない」という方でも、安心して始められます。
コンポストに興味がある方は、まずはLFCコンポストから気軽に挑戦してみませんか?

回転式コンポストの選び方・使い方~よくある失敗と解決法も解説~
「生ごみを減らせて、環境にもやさしい」、そんな魅力からコンポストに興味を持つ人が増えています。しかし、実際には「難しそう」「失敗しないかな」と不安で一歩が踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか? そんな方のために、 […]
・ 9分で読める

コンポストはホームセンターで買わない方がいい!?おすすめの方法を紹介
ごみを減らすために、コンポストに興味を持った方は多いかもしれません。そんな時、まず気になるのは「コンポストってどこで買えるの?」ではないでしょうか。 コンポストの素材はホームセンターでも取り扱っているため、最寄りのお店で […]
・ 11分で読める

コンポストトイレとは?メリットや気になる臭いのことも解説
環境に優しく災害時にも活躍することから、いま静かに注目を集めているトイレです。 アウトドアや防災意識の高まりとともに、家庭への導入事例も少しずつ増えてきました。 この記事では、コンポストトイレの仕組みやメリット、導入方法 […]
・ 10分で読める

【初心者必見】コンポストによくある失敗の原因と対策をやさしく解説
「コンポストが気になるけれど、失敗したらどうしよう…」と一歩踏み出せないあなたへ。実は、失敗も学びのチャンスなんです。本記事では虫や臭いなどの代表的なトラブルと対策をわかりやすく解説し、長い目で試行錯誤を楽しむためのポイ […]
・ 10分で読める