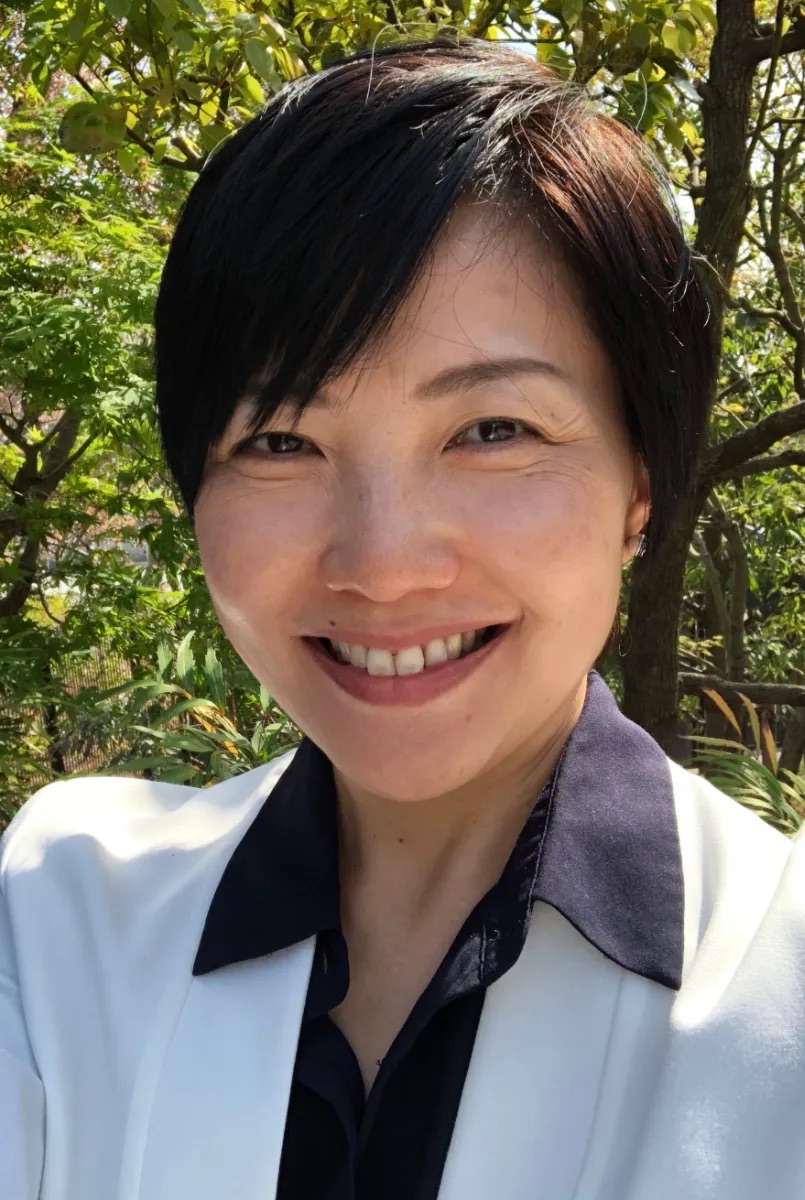非常食に野菜を取り入れる方法6選~災害時に役立つ備えを紹介~

平 希井
・ 9分で読める
Index

非常食といえば乾パンやアルファ米、カップ麺などが思い浮かびますが、意外と見落としがちなのが「野菜」です。災害時はストレスや体調の変化も重なるため、栄養バランスを意識した備えが健康を守るカギとなります。
とはいえ、「どうやって野菜を非常食に取り入れたらいいの?」「保存できる野菜なんてあるの?」という疑問もあるはず。
そこでこの記事では、長期保存に向く野菜の種類や、災害時にも役立つ備え方6選をご紹介します。あわせて、家庭菜園やコンポストを活用する方法もお届けします!
非常食では野菜が不足しがち
政府は、最低でも3日分、できれば1週間分の食料備蓄を家庭に求めています。その中でも、パックご飯やカップ麺、パスタなどの炭水化物系非常食は、手軽にお腹を満たせることから優先されがちです。
一方で、野菜の備蓄は見落とされやすく、実際に避難所で配られる支援物資も、パンやおにぎりが中心。生鮮食品を確保するのは難しいのが現実です。
だからこそ、非常食を準備する際には、栄養バランスを意識して野菜の摂り方も考えておきましょう。
(出典:内閣府「今日からできる食品備蓄。ローリングストックの始め方」)
野菜不足が引き起こす健康リスク

厚生労働省によれば、成人が1日に摂取したい野菜の目標量は350gとされています。しかし、同省が公表している「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」によると、1日の野菜摂取量の平均値は256.0gで、男性は262.2g、女性では250.6gという調査結果となりました。
野菜には、ビタミン・ミネラル・食物繊維など、体の調子を整える栄養素が豊富に含まれています。そのため、これらの栄養素が不足しがちな発災時では、便秘・貧血・口内炎など体調不良を引き起こしやすくなります。
大規模災害では避難生活が長引くケースもあるため、非常時こそ野菜の栄養を意識的に取り入れることが大切です。
(出典:厚生労働省「栄養・食生活」、「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」)
非常食に野菜を取り入れる方法6選
ここからは非常食に野菜を取り入れる方法を6つご紹介します。さまざまな方法がありますが、好き嫌いのある子どもの野菜不足には特に注意が必要です。普段から無理なく野菜を摂る方法を試しておくことが大切と言えるでしょう。
常温保存できる野菜
常温でも保存できる野菜をうまく取り入れれば、いざというときにも野菜が手に入りやすくなります。特におすすめなのが、じゃがいも・玉ねぎ・さつまいもなどの根菜類。室内の風通しの良い場所で保管すれば、1〜2週間以上の保存も可能です。
普段から買い置きしておいて、古いものから使って新しいものを補充する「ローリングストック」を試してみましょう。日常の料理にも使いやすい野菜なので、防災用として特別に意識せずに自然と備えられるのも魅力です。
冷凍保存できる野菜
冷凍庫にスペースがあるなら、下ごしらえした野菜を冷凍保存しておくのもおすすめです。たとえば、ほうれん草やブロッコリーなどは、さっと茹でて水気を切ってから冷凍することで、長期間保存できます。
冷凍野菜は災害時でも簡単に解凍して使えるうえ、加熱調理の手間も省けるのがメリットです。調理しやすい状態でストックしておけば、普段のごはんにも使える「備え」として重宝します。
ただし、冷凍野菜は停電が長引くと使えなくなる可能性もあるため、あくまで短期の停電対策として活用するのがポイント。他の保存法と組み合わせて備えておくと安心です。
缶詰やレトルトなどの加工食品
野菜の加工食品も非常時に役立つアイテムです。たとえば、野菜スープやミネストローネ、カレー、煮物の缶詰やレトルト食品などは、温めるだけで手軽に野菜を摂ることができます。
ふだんからこうした食品を多めに買っておき、使ったら買い足すローリングストックを意識すれば、無理なく備蓄できます。忙しいときの食事にも使えるので、「日常の延長でできる防災」としてもおすすめです。
乾物や漬物などの常備食
乾物や漬物などの常備食は、日持ちがするうえに栄養もしっかり補える心強い存在です。たとえば、切り干し大根や干ししいたけなどの乾物は、水で戻して煮物や汁物に使えます。
この他にも、乾燥に向いている野菜には、ニンジン、レンコン、ゴボウ、ナス、かぼちゃ、トマト、ズッキーニなどがあり、乾燥させると栄養が濃縮され、旨みが出るので出汁にもなります。
漬物やドライフルーツ、ジャムも保存性が高く、少量でもビタミンやミネラル、食物繊維の補給に役立ちます。手軽に野菜の栄養を取り入れられるので、日常づかいしながら非常時にも活かせる備えになります。
飲み物
非常時には、野菜ジュースや青汁、野菜スープなどの飲み物も栄養補給の心強い味方になります。これらは常温保存できるタイプも多く、賞味期限も長めなのが特徴です。
缶やパウチタイプの野菜ジュースは、手軽にビタミンやミネラルを補えるほか、スープなら体を温めることもできます。「食べる余裕がない時でも飲める」という点で、心身の負担が大きい災害時にも取り入れやすいアイテムです。
子どもが野菜を苦手にしている場合も、飲み物なら比較的受け入れやすく、安心して取り入れられます。
また、ミントやレモングラスなどのドライハーブはお湯がなくても水につけておくだけで香りや成分がでてきますのでおすすめです。胃に優しく、気持ちもリフレッシュできるでしょう。
家庭菜園
災害時の備えとしても注目されているのが、家庭菜園です。庭やベランダ、プランターなどを使って、トマト・葉物野菜・果物などを自分で育てておくことができます。
もちろんすべてを自給自足にするのは難しくても、「ちょっとあると助かる」野菜が手元にあるだけで、気持ちにも余裕が生まれます。
LFCの公式サイトでは、初心者でも挑戦しやすい家庭菜園の始め方が紹介されています。また、家庭菜園と相性の良い「コンポスト」を活用すれば、生ごみを肥料として再利用し、よりおいしい野菜作りにもつながります。
自家製の生ごみ堆肥で美味しい野菜をつくろう:LFCコンポスト
災害時に役立つ「コンポスト × 家庭菜園」

前述のとおり、災害時の野菜の取り入れ方には、非常食や備蓄だけでなく「自分で育てて備える」という選択肢も、防災のひとつとして注目されています。ここでは、家庭菜園と相性の良い「コンポスト」について、その仕組みと災害時に役立つ理由をご紹介します。
コンポストとは
コンポストとは、生ごみや枯れ葉などの有機物を、微生物の力で発酵・分解させて堆肥をつくる方法です。昔から日本では、家庭の生ごみや落ち葉を畑にまいて再利用するなど、自然に寄り添った暮らしの知恵として親しまれてきました。
最近はごみ削減やリサイクルへの関心が高まり、SDGsの視点からも注目されるようになっています。「使い終わったものを循環させて育てる」というコンポストの考え方は、防災や家庭菜園とも相性の良い取り組みです。
コンポストで家庭菜園をするメリット
災害時には、ごみの回収がストップすることもあります。生ごみをそのまま放置しておくと、悪臭や虫の発生、衛生面での不安にもつながります。
そんなときに活用できるのが、コンポストです。生ごみを堆肥に変えれば、においやごみの量を抑えられるだけでなく、栄養たっぷりの土で野菜や果物を育てることができます。
家庭菜園と組み合わせることで、安全で安心な野菜を収穫できるうえ、食料備蓄としても役立つのが魅力です。LFCのように手軽に始められるコンポストを使えば、日常の中でも無理なく続けられます。
よくある質問
ここからは非常食に野菜を取り入れる中で、よく聞かれる質問をまとめました。1つずつチェックしていきましょう。
Q. 非常食に適した野菜は何ですか
A. 非常食としてストックするなら、保存がきいて調理しやすい野菜がおすすめです。中でも、じゃがいも・さつまいも・かぼちゃといった根菜類は、常温でもある程度日持ちし、エネルギー源としても優秀。調理の幅も広く、日常づかいしながら備蓄できるのが魅力です。また、缶詰やレトルトの加工品、乾物などで補えば、さらに長期保存しやすくなります。
Q.非常時でも野菜を摂取できる簡単な調理法はありますか
A. 災害時は水や火が限られている状況が多いため、なるべくシンプルな調理法が役立ちます。
- 味噌汁やスープ、インスタント麺の具として乾物や冷凍野菜を加える
- ポリ袋で食材を湯煎調理する(※加熱は必要)
- 野菜ジュースでごはんを炊いて、リゾット風にする
など、簡単に作れて栄養が摂れる工夫を覚えておくと、非常時にも心強いです。
非常食でも野菜が摂れるように備えよう!
災害時はどうしても炭水化物中心の食事になりがちですが、体調を崩さないためには野菜の栄養も欠かせません。この記事でご紹介したように、非常食にはさまざまな工夫で野菜を取り入れる方法があります。
さらに、普段からの備えとして「家庭菜園」を取り入れるのもひとつの方法です。野菜を育てることで理解が深まり、子どものいるご家庭では野菜へのハードルが下がるのも、うれしいポイントとなるでしょう。
家庭菜園では、LFCの「コンポスト」を活用することで、生ごみを堆肥に変え、安心・安全な野菜づくりにつなげることができます。
日々の暮らしの中で野菜を育てることが、非常時の備えにもなる。そんな「循環する備蓄」を、この機会にぜひ始めてみてはいかがでしょうか。

防災トイレは何回分必要?選び方のポイントも徹底解説
「防災」と聞くと、なんとなく身構えてしまう方も多いかもしれません。しかし、日々の暮らしの延長でできる小さな備えが、いざというときの大きな安心につながります。なかでも忘れがちなのが、「トイレ」の備え。食料や水と同じように、 […]
・ 8分で読める

家庭でできる食育6選!お子さんの年齢に合わせたポイントも解説
「食育」とは、「食べることを通して学ぶこと」です。食べ物についての知識を増やしたり、バランスの良い食べ方や健康的な生活を身につけたりすることを指します。「食べること」は私たちの生活に欠かせない大切な要素です。食育を通して […]
・ 11分で読める

LFCコンポスト|アメリカミズアブとは?
虫の季節によく現れるのが、アメリカミズアブです。 虫は分解者としてとても優秀なパートナーなので、予防と対処をしていきましょう! ▼アメリカミズアブの成虫 もし発生しましたらHPのQ&Aを見ていただくか、LINE […]
・ 1分で読める