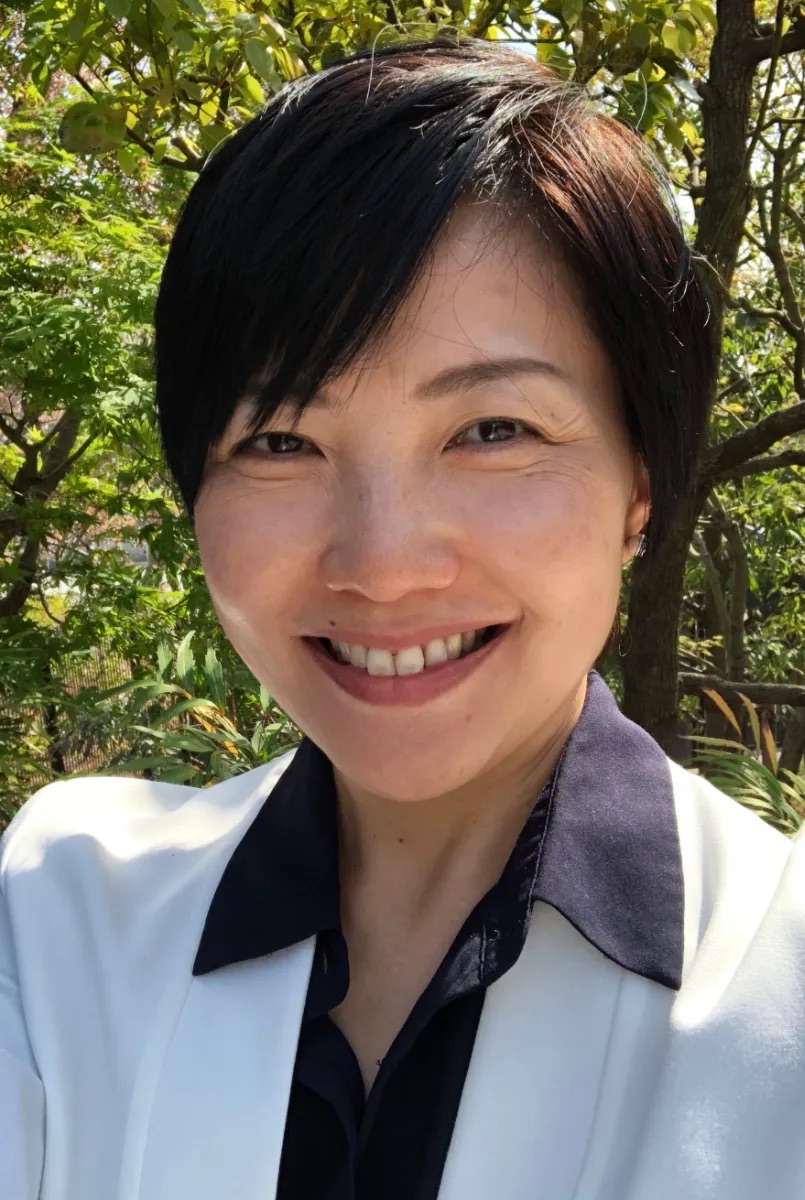コミュニティガーデンとは?メリットや参加方法を解説

たいら 由以子
・ 11分で読める
Index

最近、地域の空き地や公園で、住民同士が野菜や花を育てる「コミュニティガーデン」が注目されています。自然にふれあいながら、人とつながる新しい暮らしの形として、各地で注目されるようになりました。この記事では、コミュニティガーデンの意味や参加するメリット、始め方、実際の事例までをわかりやすく解説します。
「ちょっと気になる」「何から始めたらいいかわからない」という方も、ぜひ参考にしてみてください。
この記事はこんな方におすすめです▼
- 自然や土にふれる暮らしに興味がある方
- コミュニティ活動に参加してみたい方
- 防災や環境に役立つ取り組みを知りたい方
この記事は以下の情報が得られます▼
- コミュニティガーデンの基本的な意味や特徴
- 参加することで得られるメリット
- 始め方や参加方法のポイント
コミュニティガーデンとは

「コミュニティガーデン」とは、直訳すると「地域の庭」になります。空き地や公園の一角、学校や病院の敷地などを使って、地域の人たちが一緒に植物を育てるスペースのことを指します。
行政が管理する公園とは違い、住民が主体となって企画・運営する点が特徴です。植栽や季節のイベントを通じて自然にふれながら、ご近所の方と顔を合わせて交流できます。
もともとは1960年代後半、アメリカのスラム街で治安改善を目的に始まった取り組みですが、今では「地域のつながりづくり」や「環境への取り組み」「土地の有効活用」として、日本各地でも注目されています。
ガーデニングの知識がなくても、まずは“ちょっと土にさわってみたい”という気持ちがあればOK。
「気軽に参加できて、暮らしが少し楽しくなる」そんな魅力が詰まった場所です。
コミュニティガーデンのメリット
コミュニティガーデンには、野菜や草花を育てる楽しさだけでなく、地域とのつながりや学び、防災への備えなど、暮らしを豊かにするさまざまなメリットがあります。
ここでは、実際に参加することで得られる主な魅力をご紹介します。
地域の人と交流できる
近年は近所づきあいや世代間の交流が少なくなり、「誰と住んでいるのか分からない」と感じることも増えています。
特に核家族化が進んだ現代では、お年寄りと子どもが自然にふれあう場も限られてしまいました。
そんな中、コミュニティガーデンは年齢や職業を問わず、同じ地域の人と自然に出会える場所です。
さりげない会話の中から、地域でのちょっとした変化や困りごとが共有されることもあり、見守りのような効果が生まれることもあります。
挨拶や植物の成長を楽しむやりとりから、少しずつ関係が生まれていきます。
さまざまなことを学べる
コミュニティガーデンでは、植物を育てるだけでなく、さまざまな学びの機会が用意されています。
花壇づくりや野菜の育て方をはじめ、土壌や水質のこと、コンポストを使った循環の仕組み、地域の食文化や郷土料理についての講座など、興味に合わせて体験できる内容は多彩です。
また、活動にはガーデニングの経験が豊富な人も参加しており、実践的なアドバイスを直接教えてもらえるのも魅力のひとつ。
活動の中には、地域に暮らす海外の方と一緒に取り組むケースもあり、異なる文化や考え方を知るきっかけになることもあります。
子どもから大人まで、暮らしに役立つ知識と経験が、楽しく身につくのがメリットです。
街づくりにつながる
空き地や使われていない土地は、手入れがされないまま放置されることで景観が悪くなったり、不法投棄や防犯上の不安につながることもあります。
せっかくのスペースが、地域にとってマイナスになってしまうのはもったいないですよね。
そこで、そうした場所をコミュニティガーデンとして活用すれば、土地の有効利用につながります。
季節の草花や野菜を育てながら、定期的に手入れをすることで地域の美観も保たれ、道行く人の目を楽しませる空間になります。
また、自分たちの手で育てることで、その土地への愛着や誇りが自然と育まれるのも大きなメリットです。
「ここは自分の街」という実感を持つことは、街づくりの一歩にもなります。
防災に役立つ
コミュニティガーデンは、日常のふれあいの場であると同時に、非常時に地域を支える機能も果たします。
たとえば災害時には、ガーデンが避難場所として活用されたり、雨水の貯留設備があれば生活用水の確保にもつながります。
また、普段から野菜や果物を育てていれば、非常時の食料として活かせる可能性も。
なによりも、普段から顔を合わせている人との関係があることで、いざという時の助け合いがスムーズになるのは大きな安心感です。
このように、コミュニティガーデンがあることで、地域に“備える力”が自然と育まれていきます。
コミュニティガーデンに参加する方法

コミュニティガーデンは、特別な知識やスキルがなくても始められるのが魅力です。
もちろん、自分で仲間を集めて一から立ち上げることも可能ですが、その場合は土地の確保や資金面の準備など、負担が大きくなることもあります。
そのため、初心者の方はすでにあるコミュニティに参加するところからスタートするのがおすすめです。
ここでは、無理なく参加できる頻度や、活動場所の探し方についてご紹介します。
参加できる頻度を決める
コミュニティガーデンの活動頻度は、場所や運営団体によってさまざまです。
月に一度の草取りや、季節ごとのイベント、毎週の水やり当番まで、関わり方には幅があります。
単発の体験イベントや、数回にわたる連続講座など、初心者でも参加しやすいプログラムが用意されていることも多く、まずは見学や体験会からスタートしてみるのがおすすめです。
基本的に報酬が発生する活動ではないため、会費や参加費が必要なケースもあります。
自分の生活スタイルや関心に合わせて、無理のないペースで関われるように調整してみましょう。
「できる範囲で、少しずつ」が、長く続けるコツにもなります。
参加できる場所を探す
コミュニティガーデンに参加してみたいと思ったら、まずは活動場所を調べることから始めましょう。
全国の取り組みが掲載されている「循環型コミュニティガーデン協会」のサイトでは、地域ごとの情報も確認できます。
そのほか、以下のような方法もおすすめです。
- 「地域名」+「コミュニティガーデン」「都市緑化」「グリーンプロジェクト」などのキーワードで検索する
- 市区町村の環境課や緑化推進課に問い合わせる
- 地域の広報誌や掲示板をチェックする
活動名が違っていても似た目的のプロジェクトが見つかることもあるので、幅広く調べてみましょう。
コミュニティガーデンの事例4選
「実際のコミュニティガーデンはどんな雰囲気?」と疑問に思う方へ向けて、ここからは事例を4つご紹介します。
それぞれの活動内容や設立の背景を見ていきましょう。
LFCコミュニティガーデンみとま(福岡県福岡市)
LFCコミュニティガーデンみとまは、福岡市東区三苫にある菜園を持つコミュニティガーデンです。NPO法人循環生活研究所(通称:じゅんなまけん)が、「LOCAL FOOD CYCLING(LFC)」の理念のもと、地域内での「野菜を育て、食べて、出た生ごみを堆肥にしてまた土へ戻す。食と環境がつながった循環型の暮らし方」である、食の循環を目指して設立しました。
ここでは、菜園活動や生ごみを活用したコンポストの普及、堆肥づくり、堆肥を使った野菜の栽培講座や加工品の製造・販売会などが行われています。
ヒューゲルカルチャー農法の導入やコンポストトイレの設置など、先進的な取り組みが詰まった場所というのも大きな特徴です。
福岡市東区周辺にお住まいで、環境にやさしい暮らしや地域とのつながりに関心がある方におすすめです。
野菜づくりを通じて、日常の中で“食の循環”を体感してみたい方は、ぜひチェックしてみてください。
コミュニティガーデン牧の鼻(福岡県福岡市)
福岡市東区香住ヶ丘に誕生した「コミュニティガーデン牧の鼻」は、LFC本社オフィスから半径2km圏内に広がる“栄養循環のある暮らし”の実践の場です。
きっかけは、オフィス前に掲示した一枚のコンポスト講座のポスター。そこから地域の方々と連携の輪が広がり、土地の無償提供を受けて2024年春「子どもからお年寄りまでが集う楽園をつくる」という地域の夢を反映させたコミュニティガーデンが誕生しました。
活動内容は家庭から出る生ごみや落ち葉を堆肥にし、野菜や季節の花を育てる体験を通して、地域の中に「小さな循環」を根づかせていく試みです。
今では戸建ての方々が堆肥を家庭菜園に活用するだけでなく、堆肥が不足しがちな集合住宅から資源を回収する仕組みづくりにも挑戦しています。
「地域の人と、暮らしのなかで循環をつくっていく」そんな取り組みに共感した香住ヶ丘エリア在住の方には、ぜひ一度訪れてみてほしいコミュニティガーデンです。
渋谷リバーストリートファーム(東京都渋谷区)
渋谷リバーストリートファームは、渋谷川沿いの再生遊歩道に設けられた都市型のコミュニティファームです。
東急株式会社とUrban Farmers Club(UFC)が共同で開発・設置し、地域住民や企業メンバーが野菜づくりや固定種の育成に取り組んでいます。
UFCの代表は「渋谷の農家」として知られる 小倉崇さん。渋谷を拠点に多彩な体験の場を創造し、渋谷発の在来野菜「渋谷ルッコラ」の普及にも力を注いでいます。
畑は廃材を活用したDIY仕様で設計されており、作業のしやすさにも工夫が凝らされています。
新南口の複合施設「SHIBUYA STREAM」とも連携し、大人の部活動「STREAM農業部」の活動拠点としても活用。渋谷ならではの“未来の在来野菜”の育成にも挑戦しています。
また、ファッションの街・渋谷らしく、オーガニックコットンの栽培にも取り組んでおり、衣食にまつわる循環の大切さを体験できる場として注目されています。
都市の中心で自然とふれあいながら、食や衣の未来を考えるきっかけが得られるユニークな取り組みです。
SATOYAMA BASE 深大寺
SATOYAMA BASE 深大寺は、東京都調布市深大寺に位置する循環型コミュニティガーデンです。
農林水産省の支援を受けてモデル拠点として2024年に始動し、地域の若手農家・相田直人さんが中心となって運営しています。
活動では、家庭から出る生ごみや落ち葉を堆肥にして野菜や草花を育てる「生ごみ堆肥化による資源循環」を実践しています。
また、地域の資源を活かした柵づくりや、昆虫が棲める「バグホテル」の設置など、自然と共生するための工夫も注目したいポイントです。
ガーデンではコンポスト講座や農作業体験などのイベントも随時開催されており、地域住民だけでなく、自然や循環型の暮らしに関心のある人なら誰でも参加可能です。
参加情報はInstagram(@satoyamabase_jindaiji)で発信中されています。
地域の自然とつながりながら、サステナブルな暮らしを体感したい方にぴったりの拠点です。
私たちと一緒にコンポストをはじめませんか
コミュニティガーデンは、野菜や花を育てながら、地域の人と交流したり、自然とふれあったりできる、ゆるやかなつながりの場です。
知識や経験がなくても気軽に始められ、自分のペースで関わることができるのも魅力のひとつ。街の空き地や公園の一角で、世代や立場を超えた新しい出会いが生まれています。
LFCでは、こうしたコミュニティガーデンの支援のほかにも、家庭でできるコンポストの活用や、持続可能な食の循環を学べる講座の開催などを通して「都市に暮らす人が自分らしく暮らしに“循環”を取り入れる」ための活動を広げています。
さらに2024年には、 「循環型コミュニティガーデン協会」 を設立し、都市と自然が共生する仕組みづくりを全国規模で推進しています。
ベランダ菜園から始めてみたい方や、地域で何かしたいけど一歩踏み出せずにいる方も、ぜひLFCの情報をのぞいてみてください。

おしゃれな家庭菜園を作りたい!“映える”菜園の作り方6ステップ
最近、おしゃれな家庭菜園を始める人が増えていることをご存じですか? ガーデニングと聞くと、地味で難しそうなイメージがあるかもしれませんが、今は「センスよく見える!」「写真に撮りたくなる!」と、インテリア感覚で楽しむスタイ […]
・ 11分で読める

家庭菜園の栽培カレンダー|初心者におすすめの年間プランも紹介
家庭菜園を始めたいけれど、「何をいつ育てればいいのか分からない」と悩むことは多いです。そんな初心者の方に向けて、年間の栽培スケジュールをわかりやすくご紹介します。家庭菜園は計画が大切です。季節ごとに育てやすい野菜を選び、 […]
・ 12分で読める

家庭菜園を始めよう!プランターの選び方とおすすめの野菜
家庭菜園に興味はあるけれど、「広い庭がない」「初心者だから難しそう」と思っていませんか?実は、プランターを使えば、ベランダやちょっとしたスペースでも手軽に野菜作りを楽しめます。自分で育てた野菜は格別のおいしさがあり、無農 […]
・ 11分で読める

ぼかし肥料の作り方~初心者でも簡単にできる方法を解説~
家庭菜園やガーデニングをしていると、「ぼかし肥料」を目にする機会も多いのではないでしょうか。ぼかし肥料は有機栽培に適した自然派肥料で、初心者でも簡単に作れます。ぼかし肥料は環境に優しく、即効性と持続性のバランスが良い点が […]
・ 8分で読める