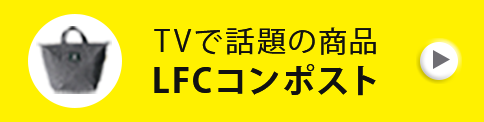家庭でできる食育6選!お子さんの年齢に合わせたポイントも解説
「食育」とは、「食べることを通して学ぶこと」です。食べ物についての知識を増やしたり、バランスの良い食べ方や健康的な生活を身につけたりすることを指します。
「食べること」は私たちの生活に欠かせない大切な要素です。食育を通して、大人も子どもも健やかに成長し、よりよい生活を送ることができます。
今回は、そんな「食育」とは何かを改めてお伝えするとともに、学校で行われる食育を家庭でも気軽に取り入れられる方法をご紹介します。未就学児から高校生まで、お子さんの年齢に合わせたポイントも解説しますので、家族みんなで楽しく食育に取り組んでみましょう。
この記事は以下の方におすすめです▼
- 食育とは何か知りたい方
- 子どもの好き嫌いに悩んでいる方
- 家庭でできる食育方法を知りたい方
この記事は以下のことがわかります▼
- 食育とはなにかわかりやすい言葉で解説
- 家庭でできる食育の気軽な取り組み方法
- 子どもの年齢にあわせた食育のポイント
食育とは

食育とは、「食べることを通して学ぶこと」を指します。食事は生きるために不可欠な要素であるため、食べ物についての知識を増やしたり、バランスの良い食べ方や健康的な生活を身につけるために、食事を学ぶことが食育です。
たとえば、
- 野菜や果物がどのように育つのかを知る
- 食事のバランスを考える
- 食事を楽しむ気持ちを持つ
- 食べ物を大切にする心を育てる
- 自分や家族の健康を意識する
こういったことを、子どもから大人まで学んでいきます。
2005年には「食育基本法」という法律も制定され、家庭・学校・地域がみんなで食育に取り組むことを推奨しています。「食育」というと少し難しい印象がありますが、食育を通して知識を身につけ、食事の楽しさを知ることが目的です。また、食育は学校でも学ぶものですが、実はご家庭で取り入れられる気軽な方法もたくさんあります。
食育のメリット
なぜ食育が大切なのかというと、
- 健康な体をつくる
- 心の安定を保つ
- 食事のマナーが身につく
- 感謝の気持ちが育つ
以上のようなメリットがあるからです。食育の持つメリットを1つずつチェックしていきましょう。
健康な体をつくる
食育によって食材の栄養素、バランスの良い食事を知ると、病気を防ぐことができます。また、好き嫌いをしない心がけもできるため、健康な体をつくることにつながるのは、大きなメリットです。
食事というと「ダイエットを意識している」という方もいますが、ボディメイクやダイエットをする方にも食育はおすすめです。食べ物の知識があれば食べすぎによる肥満や過度なダイエットによる栄養失調も防げます。
心の安定を保つ
食育の中には、「食事を家族で一緒に摂る楽しさを学ぶ」ことも含まれます。そのため、食事が適切なコミュニケーションの場になることもわかり、心の安定が図れます。
仕事に家事にと忙しい方にとっては、家族とのコミュニケーション不足で悩みがちです。食育を学ぶと、一緒に食卓を囲むことの所属感や安心感も身につき、心の支えにつながります。
食事のマナーが身につく
日本の食文化を大切にするうえで食育では、「箸の正しい使い方」や「美しい食事の姿勢」といった基本から、「一緒に食べる人に合わせた食べ方」や「料理の取り分け方」など、相手を思いやる心を育むことも学びます。
マナーが身につくと食事の時間がより楽しくなり、外食や特別な場でも自信を持って過ごせるようになります。食卓を囲みながら自然と日本の食べ物や良き習慣を学べることができるとは、食育の大きな魅力です。
感謝の気持ちが育つ
食育によって「食材の作り方」「調理方法」「どんな人とどうやって食べると楽しいのか」を知ると、感謝の気持ちが育ちます。調理してくれた方への感謝や食材を育ててくれた方への感謝、一緒に食べてくれる方への感謝など、感情が豊かに育つのもメリットです。
また、感謝の気持ちを持つことは食事を無駄にしない、適量を残さず食べるという食事マナーにもつながります。
子どもの年齢に合わせた食育のポイント
食育にはさまざまなメリットがありますが、大切なのは「食事の楽しさを知る」という目的です。食育を「難しいもの」として考えないように、子どもと行う食育には年齢を考慮したポイントを押さえておきましょう。
- 未就学児
- 小学生
- 中・高校生
のそれぞれを解説します。
未就学児
未就学児への食育では、まず「食べることを楽しむのが最優先」です。好き嫌いや食事のマナーなど、あまり厳しくすると食事に対して苦手意識が芽生えてしまいます。たとえば、好きなものを増やしたり、全体の量を減らして「完食する達成感」を教えてあげるのも効果的です。おかわりができた!という体験も、食事に対する自信につながります。
小学生
小学生への食育は「基本的な食習慣を身につける」のが大切です。学校へ通う時間を考えて、朝食を抜かないように1日の生活リズムを整えつつ、1日3食を楽しめるようにしましょう。栄養バランスや配膳、基本的な食事のマナーもわかる年齢なので、少しずつ食事に関する知識を学んでいくのもポイントです。
中学生・高校生
中学生、高校生の生活は勉強や部活動、友人との交流など忙しくなります。食事が不規則になりやすい時期だからこそ「健康を意識した食生活」がポイントです。食事を抜いたり、ファストフードばかりにならないような栄養バランスを心がけるとよいでしょう。
また、ダイエットを意識する子もいます。間違った方法や極端なダイエットで栄養失調にならないように栄養素の知識も必要です。自立に向けて自炊のスキルを身につけるのも、中学生・高校生の食育の特徴です。
家庭でできる食育6選

食育は家庭でも気軽に取り入れられます。
- 一緒に食材を買いに行く
- 一緒に食べる
- 料理や準備・片付けを手伝ってもらう
- 1日3食規則正しく食べる
- 食事のマナーを教える
- 野菜や果物を育てる
この6つの方法を詳しく見ていきましょう。
一緒に食材を買いに行く
毎日の食事のお買い物に、子どもを連れていくのも食育の1つです。売り場には季節の野菜や果物が販売されているため、「旬」とは何かを学べるでしょう。また、鮮魚コーナーには切り身ではない一匹丸ごとの魚や、皮が付いたままの海老など、食材そのものを見て知ることができます。
お買い物では、食材の選び方や値段、産地や旬の食べ物を話すことで、食育につながります。
一緒に食べる
家庭でできる気軽な食育の1つに、「一緒に食べる」ことが挙げられます。ただ一緒に食事をするだけ?と思う方もいるかもしれませんが、核家族化や両親共働きの家庭が増えている中で、家族全員が一緒に食卓を囲むのは難しいケースも増えています。
その中で、一緒に食事をすると、食事によるコミュニケーションや食事中のマナー、また会話し食事を楽しむことで得られる心の安定感などが身につきます。一緒に食べると早食いや偏食、テレビやスマホを見ながらの「ながら食べ」を防ぐためにも効果的です。
料理や準備・片付けを手伝ってもらう
食事の支度や後片付けも、食育の一環です。お手伝いは年齢に応じて方法を変えてみましょう。たとえば、最初はテーブルを拭く、お皿やお箸を並べる、少し年齢が上がると野菜を洗ったり卵を割るなどの調理補助をお願いしてみるのがおすすめです。小学生以降は、包丁や火を使う練習も楽しく食事の仕方を学べます。
また、片付けや調理中には生ごみが出ます。これを「再利用」するのも食育の一つです。たとえばコンポストを利用して、生ごみを堆肥に変えることで「食事で発生した生ごみを堆肥づくりに利用し、また食材を育てる糧にする」という流れを学べます。
コンポストとは、生ごみや落ち葉などの有機物を微生物の力で分解し、堆肥として再利用する仕組みです。最近では家庭で取り入れやすい小規模なコンポストも見つかるため、食育の一つとして「食事の片付け」を「堆肥づくり」につなげ、リサイクル意識を身につけるのもおすすめです。
こうしたお手伝いは家族の一員としての役割を認識し、また、食材がどう調理されてどう提供するのかを学び、自分が支度した食事をおいしく食べてもらう喜びを実感できます。
1日3食規則正しく食べる
1日3食規則正しく食べることは、1日に必要な栄養素を摂るだけでなく、生活リズムも整う食育です。特に朝食を抜いてしまう方は多くいますが、朝食は1日のエネルギー源になります。学力や体力、精神力などさまざまな面に影響すると研究結果も出ているため、ぜひ1日3食の規則正しいリズムを整えてみましょう。
1日3食の食事を習慣づけるには、少しずつ生活のリズムを変えていくことが効果的です。食事の時間を決めたり、忙しい時間帯の朝食には手軽に食べられるものを用意したりなど、家庭にあう方法を見つけてみてはいかがでしょうか。
食事のマナーを教える
食事のマナーは大切な食育の1つです。小さなころからの積み重ねなので、発達に応じて継続的に学んでいきましょう。食べるときの姿勢や箸の持ち方・使い方、「いただきます」などの挨拶や一緒に食べる人への配慮など、さまざまなマナーを少しずつ身につけていくと効果的です。
子どもに食事のマナーを教えるとき、大切なのは「大人が見せる姿勢」です。大人も食事のマナーが守れているかどうか、ときには振り返って考えることで、家庭の食育はスムーズに進みます。
野菜や果物を育てる
野菜や果物を育て、家庭菜園を楽しむのも食育の大切な一歩です。いずれ食卓に並ぶこととなる野菜や果物を、一から育てることで「食べ物の大切さ」を学べます。家庭菜園に触れる中で「こんなに育てるのは大変なんだ」「収穫ってこんなに楽しいんだ」と気づきや感動が得られるでしょう。好き嫌いが多い子どもも、自分で育てた野菜なら興味を持ってくれるかもしれません。
この食育の学習効果を高めるためには、先ほどの「コンポスト」で作る堆肥を利用するのがおすすめです。堆肥は野菜・果物作りには欠かせない要素です。「家庭で発生した生ごみ」が「野菜を育てる堆肥になる」という流れは、一連のサイクルを体験できる良い機会になります。
コンポストとは、「畑の近くにある大規模なもの」というイメージが強いかもしれません。LFCコンポストは、都会のベランダでもコンポストを気軽に始められる「バッグ型のコンポスト」を用意しています。コンパクトな作りのため、置く場所を選ばず、親子で一緒にコンポストを始めやすい点も特徴です。
野菜や果物を育てる中でより食育効果を高めたい方は、ぜひコンポストにも注目してみてください。
家庭での食育にはコンポストもおすすめ!
食事の楽しさを知るため、健康的で豊かな生活を送るために大切な食育。家庭でもできることはたくさんあるため、ぜひ気軽な方法を試してみましょう。
家庭での食育のひとつに、コンポストの利用があります。コンポストとは生ごみや落ち葉などを分解して堆肥にする仕組みです。家庭菜園などで活用することで、食材の育て方から作り方、生ごみをまた土に戻しコンポストとして利用する一連のサイクルを学べます。
コンポストは「大がかりなもの」という印象がありますが、LFCコンポストはご家庭のベランダでも使えるバッグ型です。家庭の生ごみを投入して良くかき混ぜるだけで堆肥が作れる仕組みのため、気軽に「家庭菜園から始める食育」を学べます。
気になる方は、ぜひLFCコンポストをチェックしてみてください。